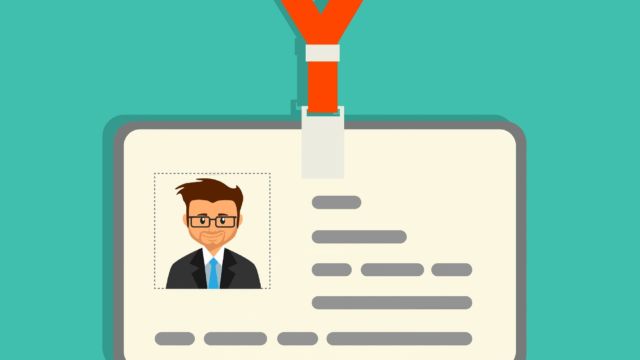・独立開業や新規事業としてフランチャイズを検討している個人や法人
・フランチャイズ本部への転職や就職を考えている方
にむけて、本記事では、おすすめのフランチャイズを紹介しています。
私自身は、コンサルタントとして20年のキャリア、在職中には創業から2年で100店舗まで急成長したフランチャイズ本部の立ち上げコンサルに従事、今は事業会社の役員として新規事業に多くのフランチャイズ加盟の検討を行っています。
もちろん検討にあたって、単なる資料収集にとどまらず、営業担当者から話を聞いたり、実店舗の見学や導入企業から生の話を聞いています。
ちなみに、今回紹介するフランチャイズは、全て私自身が直接話を聞いたものばかり。逆に言えば、自分で研究、事業性を評価したものだけを紹介しました。
そういう意味では、ネット上の広告記事とは違う視点で紹介できていますし、信憑性もそれなりに保証できます。
普段なら文章を強調したりもしますが、今回は出来るだけ私の色をつけないよう、装飾なしで書いています。(内容は主観に満ちていますが)
読みにくいですが、ご容赦下さい。
何を基準におすすめしているか?
初めにこれを明らかにしておく必要があるでしょう。
私がフランチャイズを評価する基準は次の3点。
・事業の市場性
・出店可能なエリア
・競合との優位性
これだけです。
それ以外は考えなくてよいと断言できます。
本部の収益シミュレーションは、90%あてになりません。
市場に魅力があれば、結果(利益)はついてくるでしょう。
でも契約の関係上、出店できるエリアに制約があれば、いくら事業に魅力があっても断念せざるを得ないですよね。
エリアに制約がなく、好きな所に出店させて良いというなら、私なら「カーブス」を選びます。(実際には新規募集はストップしています)
よく本部のサポート力の大切さを言う人がいますが、私から言わせれば、とんだ筋違いで「バカ」と言いたいです。
市場に将来性があり、本部が成長を続けるなら、本部のサポート力なんて、後から幾らでもついてきます。
実際に自分で話を聞いて、この3点の基準を満たしているフランチャイズが次の5つです。
おすすめのフランチャイズ
・わおん
・てらぴあポケット
・24時間フィットネス
・キッズデュオ
・ベンリー
この5つです。
参考までに、事前には候補にあげつつ、最終的にはおすすめから外したフランチャイズと、その理由です。
・おたからや(買取専門店)・・・買取品を集める仕組みが不明。リユース市場はよりメルカリなどのCtoCへ向かう。
・やどかり弁当(宅配弁当)・・・参入可能な業種が狭いため、ここではおすすめしにくい
それでは、早速ですが見て参りましょう。
わおん

事業の概要
業種:障がい者グループホーム
障害者総合支援法に基づく障害者福祉サービスです。
障がい者グループホームとは、身体・知的・精神障害者などが世話人などの支援を受けながら、施設で共同生活を送る場です。
利用者は国や市からの補助を受け、月の自己負担5~7万円で住まいと食事のサポートを受ける事ができます
運営:株式会社アニスピホールディングス
代表の藤田英明氏は、高齢者向けデイサービスのフランチャイズチェーン「茶話本舗」を立ち上げた実績があります。(今は経営譲渡)
ビジネスモデル:
障がいを持った成人に対し、住まいと食事の提供と生活支援を行います。
行政の支援により、入居費用の一部は行政が負担します。
行政に事業開始の申請を行い、指定を受けて初めて事業が行えます。
指定を受けるにあたっては、施設の広さや人員に基準があります。
わおんの場合、一軒家に3~5名が入居するのが通常のパターンのようです。
自立支援の前提のもと、仕事や生活は入居者個々が自分で選ぶことができます。
障がい者グループホームの市場性
国内の障がい者数(身体・知的・精神)は人口の7.3%にあたる930万人。
この人口は増え続けています。
障がい者の生活は、家族と同居する、施設に入居する、自力で生活する、病院に入院するのいずれか。
病院のベッド数が不足し、支援する家族も高齢で障がい者を支える事ができなくってきており、今後ますますニーズが増えるといいます。
わおんの試算によると、全国で4万事業所が不足、まだまだ数が足りていないとの事です。
このマーケットの需給ギャップを背景に、わおんは急激に加盟数を伸ばしています。
現在、契約レベルでは500施設の出店が決まっているようです。(2020年3月時点)
これから新規出店を目指す方には、エリア選定で制約を受けるケース(出店不可のケース)が出て来そうですので、加盟判断は早めにする必要ありです。
わおんの競争優位性
行政のサポートと収益性の高さにより、注目を集める障がい者グループホーム。
フランチャイズを展開する新規参入事業者も増えています。
競合他社と比較したわおんの優位性は、わんちゃんと入居者が同居するユニークなサービスです。
一般的に、グループホームの経営は、単なる寝場所の提供になる傾向があります。
コミュニケーションが疎遠となり、入居者とスタッフ、入居者同志のトラブルも起こりかねません。
逆にサービスを手厚くすると、運営スタッフに過度な負担を強いることになり離職原因にも。
同居のわんちゃんが、施設内のコミュニケーションの結節点になり、スタッフや入居者の癒しや、スタッフの負担軽減になって、これがわおんの最大の魅力です。
わおんの収益性
わおんのフランチャイズの特徴はレベニューシェア方式による美味しいところ取りの契約形態。
採り入れたいノウハウやサービス、またブランド利用の有無により、費用が変動します。
加盟金など本部に払うお金以外に、物件取得費や内装工事費、備品代などがかかります。
6事業所契約の場合
・加盟金 500万円
・初期費用 1357万円(加盟金・物件取得費・内装工事費・備品)
・年間売上 9342万円
・年間利益 2128万円
*投資回収期間 7.6ヶ月
以上、わおん公式サイトより
公式サイトを参考に、よりシビアに見積ます。
契約:
単店出店は、投資効果の面でも、営業面でも人材面でも非効率な印象。
たかがと言えば失礼ですが、3人の受入のために、人を雇ってビジネスしますか?
3人のうち、1人でもキャンセルでれば、それだけで売上30%減です。
こんな経営、誰もしないですよね。単店出店とかは止めた方が良いです。
地域にドミナントで6店舗以上の出店を本部が推していますが、これはその通りだと思います。
初期費用:
各店舗ごとに、取得費や工事費、備品代などで1店に100~200万円の費用との事ですが、これは物件の状態により変動します。
特に消防設備が気になります。
一般の民家に消防設備があると思えないので、事業開始に当りフル投資が必要となります。
次に物件取得費ですが、敷金を家賃の2か月程度と見込んでいるため、開業する地域により全然違ってくるでしょうし、東名阪で開業するなら、この金額では難しいです。
また家賃保証を求められるケースがあり、信用力に応じて、家賃の0.5~1ヶ月分ほど余分にかかります。
運転資金:
初期費用の中に運転資金が入っていないようです。
行政からの入金は後になりますし、すぐに満室になる訳ではないので、開業より6ヶ月程度の運転資金は別途用意する方が賢明です。
売上:
一斉オープンして、一斉に入居者が決まった場合のシミュレーションなので、これはあてになりません。
行政への指定申請の関係でオープン時期はマチマチ、集客も一気に満室経営とはいきません。
稼働率60%程度でシミュレーションする方が賢明です。
以上を元に、再シミュレーションした場合、投資回収期間は成功して3年以上と見込んだ方が良いでしょう。
わおんのリスク
わおんのビジネスモデルは国の福祉行政の影響を受けます。
3年に一度の大きな改正、毎年小さな改正があります。
改正の内容次第で、事業に大きな影響を受ける場合があります。
創業者の藤田氏についてが2つ目のリスク。
茶話本舗の時は、加盟者との契約トラブルを抱えていました。
藤田氏自身の体質がベンチャーで、大きなビジョンをまずかかげ、詳細は走りながらというスタンスが強いためです。リーダーシップと暴走が紙一重です。
急拡大するフランチャイズにありがちです。
わおんの現状は不明。急拡大している点は、前回と変わらない姿です。
てらぴあポケット

概要
業種:児童発達支援事業、児童福祉法に基づくサービス
発達障害のある未就学児に対して、社会で安心して暮らせるよう療育のサービスを提供します。行政からの補助を受けて、利用者家族は1割負担、残りは行政が負担します。
運営:オークニ商事株式会社
障害児通所事業(放課後等デイサービス)の教室運営を100教室以上。
業界大手に属します。
児童発達支援の市場性
発達障害をお持ちの子どもは全体の6.5%と言われており増加傾向です。
一方で、児童発達支援事業のサービスを受けている比率は、ほんの10%程度。
まだまだサービスが世の中に浸透していない状況。
さらには2019年10月より幼児教育無償化がスタート、児童発達支援も無償化対象です。
幼児の分野は、国が投資する戦略分野です。
てらぴあポケットの競争優位性
児童発達支援事業の業界でトップを走るのは、コペルプラス(FCあり)、リタリコ(直営のみ)の2強です。
両社ともに開校が増え教室は飽和状態、特に都心部で開校できる場所が限られてきています。
市場性が充分にある中で、三番手グループのてらぴあポケットにも、まだ充分に開校できるチャンスがあると見込み、おすすめで紹介しています。
ただし、優れた教育プログラムを持つコペルプラス、マーケティングに長けたリタリコと比べ、てらぴあポケットの優位性は乏しく、あくまで市場に開校余地があるとの評価です。
てらぴあポケットの収益性
てらぴあポケット公式サイトで紹介されている収益性です。
・初期投資総額 約726万円~
・月売上 330万円
・月利益 115万円
*開校4か月目で黒字化。投資回収1年以内。
運転資金が必要:
上記シミュレーションは、1日の利用定員10名に達した際の売上です。
この事業の収益面での難点は、行政からみた必要人員数があり、人件費が固定化されること。
公式サイトで書かれている人件費は月156万円、これは仮に売上が100万円としても削ることの出来ない費用であり、利用者が集まるまでは赤字経営(運転資金が必要)です。
したがって初期費用とは別に、600~1000万円程度の資金が別途必要です。
以上のような制約はありますが、サービス当りの単価が12,000円/人程度。
介護事業や放課後等デイサービスの報酬単価と比べて高く、高収益事業です。
てらぴあポケットのリスク
わおんの所でも書きましたが、こういった国の政策に左右される事業は、国の制度変更の影響をもろに受けます。
したがって、高い報酬単価が未来永劫継続するかは、誰にも分からないです。
この点が最大のリスクです。
もうひとつのリスクは人材の採用や雇用。
人が足りないと売上が下がるどころか、最悪はサービス休止の措置を受けることとなります。
24時間フィットネス
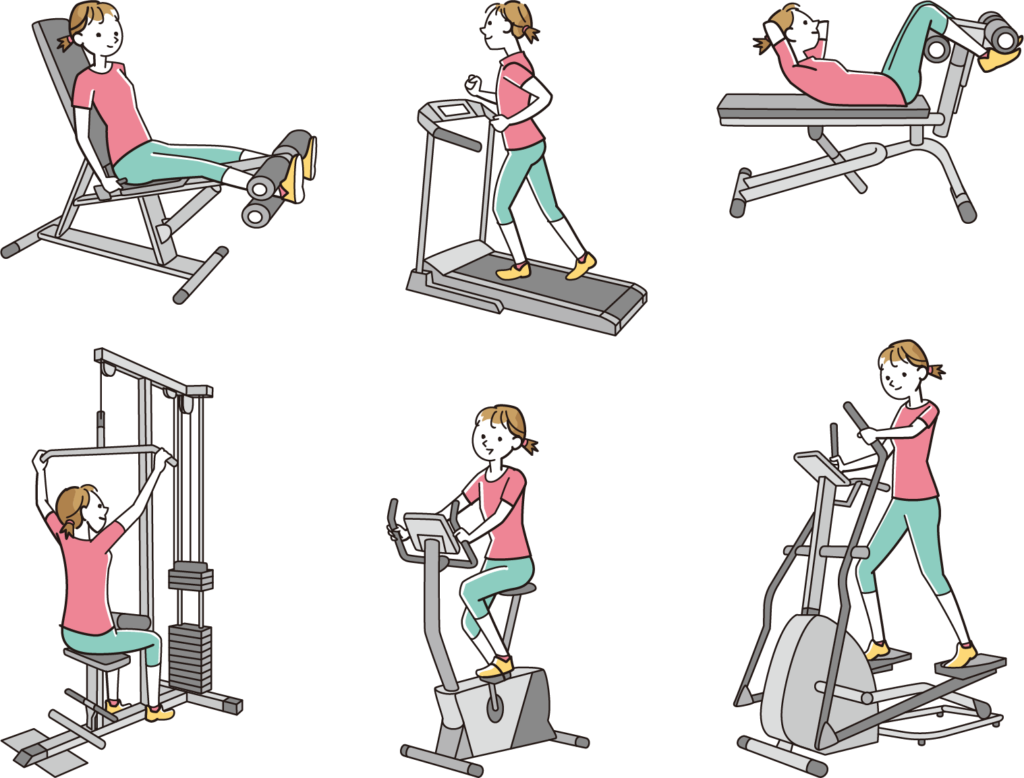
概要
業種:フィットネスクラブ(24時間営業)
立ち上げコンサル:ATカンパニー株式会社
本件はフランチャイズ契約とは違います。
開業時のコンサルティング(運営ノウハウの提供、マシン機材の導入など)のため、加盟金や月々のロイヤリティは発生しません。
24時間フィットネスの市場性
アメリカのフィットネス人口「5720万人」に対し、日本のフィットネス人口は「424万人」と増加の余地があります。
人生100年時代の到来と言われ、老若男女問わず健康志向ブームの勢いが増しています。
その一方、従来の総合型フィットネスは、施設やサービスを全て利用する会員は少なく、実際はマシーン(ウェイトトレーニング、ランニング)のひとだけ、スタジオレッスンだけ、サウナだけ、といった利用の仕方が多く、会費が1万数千円と高額でした。
マシーン利用者にフォーカスし、余分なプールやスタジオを省き、設備投資を下げ、会費に反映させたリーズナブルな小規模フィットネスとして生まれたのが、エニタイムフィットネスやジョイフィット24といった24時間フィットネス業態です。
そのような変化に乗り、エニタイム約700店、JOYFIT約300店と爆発的に成長、現在は両社ともにフランチャイズ加盟募集は終了、新たな事業者の出現が待たれます。
24時間フィットネスの競争優位性
フィットネスクラブは初期投資が多大です。
一般的に8000万円から1億円程度の初期投資が必要と言われており、大半はマシン機材の購入費用です。
ATカンパニーが提供する24時間フィットネスの場合、独自ルートで開発した機材により半額の4,000万円から5,000万円でスタートすることができます。
また24時間フィットネスは、マシーンのみとなるため、スタッフが少数で対応可能、人材不足の環境にあった事業モデルです。
24時間フィットネスの収益性
詳しい収益性は非公開です。
ATカンパニーの事業説明会への参加が必要となります。
24時間フィットネスのリスク
フランチャイズでないため、開業後の運営は全て当事者で行うこととなります。
個々の経営力、集客力でエニタイムやJOYFITなどの大手チェーンと戦うことになるのがリスクです。
キッズデュオ

概要
業種:英語で長時間預かる学童保育
共働き世帯が、学校の後、子供を預ける英語専門(ネイティブがスタッフ)の学童保育。
運営:株式会社拓人こども未来
会社名を聞いてもピンとこないかもしれません。個別指導大手の「個別指導スクールIE」、「やる気スイッチグループ」と言った方が分かりやすいかもです。
学童保育・子供英会話の市場性
キッズデュオの市場性を検討するにあたり、その分析対象は学童保育と子供英会話の両方になります。
「学童保育=共働きの家庭対象」が、英語で預かることにより、(共働きに関係なく)英会話に通わせたい家庭の取り込みに成功しています。
実際、キッズデュオに通う子供の半数は、専業主婦の家庭です。
2018年の学童保育は全国で約25000ヶ所、利用者は123万人。(厚生労働省)
20年間で利用者は約5倍に膨れ上がり、需要の高まりに施設整備が追い付かない状況、潜在的な待機児童は40万人、保育園を卒園した子供の行き場がなくなる「小1の壁」として社会問題化しています。
背景には、働く女性(共働き世帯)の増加です。子供の減少率を、働く女性の増加率がはるかに上回っているからです。
小学校が英語の授業を始めるなど、英語教育の強化を進める文部省ですが、TOEFL順位でアジア30ヶ国中27位(ちなみに1位はシンガポール、韓国9位、中国16位)と、グローバル化が進む中で英語が話せる人材が圧倒的に不足しています。
使える英語が習得できる臨界期は9歳と言われ、子育て世代の関心は、より幼児期の教育へと向いています。
キッズデュオの競争優位性
優位性は英語を話すネイティブスタッフの質と、知能教育プログラム。
アメリカに採用センターを構え、教育学部の出身者や教育経験者の採用と育成に力を入れています。
単に預かるだけではなく、預かりながら知能教育をオール英語で行うプログラムが提供可能なのは、グループが50年にわたり提供してきた幼児教育ノウハウや英語教育ノウハウがベースにあるから。
やる気スイッチグループは、元々は英語塾が事業の成り立ちです。
この2つのバリューにより平均月謝が4~5万円の高単価なビジネスが実現できています。
この2つ、新規参入事業者にとって、大きな壁となる事でしょう。
簡単にライバルが参入できない優位性を持っています。
キッズデュオの収益性
キッズデュオを始めるにあたって最大の障壁は初期費用の高さです。
・初期費用(加盟金や設備資金等) 約2,500~3,000万円
・年売上(1年6ヶ月後) 6,000万円
・年利益(1年6ヶ月後) 2,000万円
半年で黒字化、2~3年で初期投資回収のシミュレーションです。
黒字化に必要な生徒数は70名目安です。
2026年までに1000教室との目標をキッズデュオは掲げています。
ただし、、、月5万円の教育費は、かなり利用者を選びそう。
共稼ぎ年収1000万円以上、かつ教育熱心な子育て世帯(30~40代)が対象になるでしょうか。
首都圏、名古屋、京阪神くらいしか市場が無いような。
それ以外の地域で、果たして損益分岐点の70名すら集客に苦労しそう。
この辺りは本部に確認する必要がありますね。
加盟条件は法人であったかと。
キッズデュオのリスク
何と言ってもスタッフ(英語を話す外国人)の採用、それ以上に外国人をマネジメントすること、これに尽きます。
スタッフ全員外国人、彼らを1人の管理者(たぶん日本人)が束ねる。そういう経験が豊富な人か、相当にマネジメントに長けた出来る人材でないと。
ニーズは間違いなくあるでしょうし、社会問題化していて政府の支援も期待できるので、複数教室を運営すれば相当な事業に育ちそうですが、この1点だけが唯一の気がかりです。
ベンリー

概要
業種:生活支援サービス
分かりやすく言えば「便利屋」です。エアコン掃除、水廻りの修理、ハウスクリーニング、庭木の剪定など、身の回りの様々な困りごとに対応する業種
運営:株式会社ベンリーコーポレーション
創業30年。元は創業者自体が「街の便利屋さん」。地域の中で取り組んできた事をフランチャイズモデルとして標準化に成功。
生活支援サービスの市場性
エアコン掃除や庭木の剪定などは、以前は家族の誰かが会社が休みの日にやっていたこと、「無償労働」が従来でした。
ところが、この無償労働が有償化されたことより、生活支援サービスの市場が出現しました。
市場が出現した背景は、高齢化社会と核家族化。
特に都市部の高齢化は深刻で、独居高齢者や老々介護が社会問題化。
そのような世帯では、エアコンを掃除したくても、家具を隣の部屋に移動したくても、その労働の担い手が居ないのが実情。
人手不足は、企業やお店の中だけでなく、家の中でも実は起こっているのです。
実際、ベンリーが提供するサービスも、半数以上が60代以上からの依頼のようです。
現在、介護保険内で提供されているサービスも、国の財源の問題から、どんどん民間委託(保険外)へシフトしていくのは間違いないです。
生活支援サービスとは、高齢者向けビジネスであり、更に高齢化が進む社会において成長が期待できる事業です。
ベンリーの競争優位性
ずばり競争力の源は人的サービス、これに尽きます。
サービスが良いと評判の街の便利屋さんに注文が集まります。
良いサービスは、「便利屋」として対応できる技術の幅、高齢者から信頼されるコミュニケーション力や人間力、この2つ。
ベンリーは、以前なら個々に頼っていた「便利屋のセンス」をフランチャイズで標準化しました。
その方法は、53日連続でおこなう合宿型研修トレーニングです。
ベンリーのフランチャイズで働く全てのスタッフに、この研修参加は義務付けられ、泣き出す、逃げ出す人間も出るほどにハードな内容。
100種類の技術と、便利屋としての精神性を叩き込まれます。
ちょっと宗教じみた所がありますが、逆に言えば、どこも真似のできない内容。
この教育制度が評価され、厚生労働省からも公的介護保険外サービスの好事例として紹介されています。
いわば便利屋として国から「お墨付き」を貰っています。
ベンリーの収益性
・初期費用(加盟金や資材・機材、研修費) 約900万円
・その他の初期費用 物件取得費や内装工事費
キッズデュオほどではないですがベンリーの初期投資額も大きいです。
また、安定事業ではありますし、将来性もありますが、ものすごく利益が出る事業とも言えません。
初期投資の回収には5年はかかると考えておいて間違いないです。
ベンリーのリスク
高齢者マーケットを対象にしているにもかかわらず、介護保険制度をあてにしていない点は、私にはプラスの評価材料です。
サービスの内容は違いますが、高齢者を対象にしている事業に「カーブス」があり、こちらは高収益です。
したがってリスクらしいリスクは無いのですが、強いてあげれば、労働基準法無視、社会問題にもなりそうな53日間の合宿研修や、フランチャイズ加盟店の商圏エリアの狭さなど、所々に伺える本部の強気な姿勢が、私にはリスクに映ります。
このあたりは確認する必要があるでしょう。
フランチャイズ業界を研究するには
可能な限り、色んな種類のフランチャイズ業態より話を聞いてみることが近道です。
フランチャイズの業界研究方法は、
・フランチャイズショーへ行ってみる
日経が主催するフランチャイズショーは、年1回、東京ビックサイトで開催される日本最大規模のフランチャイズに関する展示会です。毎年、多くの方が訪れ活況です。(2020年は残念ながらコロナウィルスの関係で中止となりました)
2021年からはフランチャイズビジネスEXPOも開催され、ますますビジネスショーも活性化しますね。
もうひとつ。ウェブで研究するなら、フランチャイズ紹介サイトがあります。マイナビ独立やフランチャイズの窓口は、多くの情報が掲載されています。
東京の展示会にはなかなか行けないという人、年1回の開催まで待てないという方は、とりあえず登録(無料)です。
フランチャイズ本部におすすめ転職エージェント
フランチャイズ本部は求人数そのものが少なく、結果的に狭き門です。
したがって、主には営業系に強い転職エージェントに複数登録し、非公開求人含めて、紹介してもらうのが、賢い方法です。
業界最大手のため、転職を考えるならまず登録するのがリクルートエージェント。
一方、管理・専門職、ミドル・ハイクラス向けの高年収層(年収600万円以上)に特化したJACリクルートメント。既にフランチャイズ加盟開発の経験があるなら、こちらも狙い目です。
まとめ
いかがでしょうか?
わりと名の知れた企業が多くなり、手堅くまとめすぎたと思いますが、今後、面白いフランチャイズが出てきたら、新たに紹介していきます。
逆に、今回紹介した先も順次更新します。場合によっては取り下げも。
出来るだけ知り得る情報を集めて書きましたが、全てを鵜呑みにせず、加盟は自己責任で判断をお願いします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。